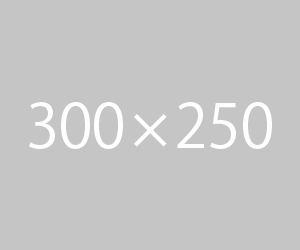先日、NPO法人日本不妊カウンセリング学会が主催する学術集会に参加してきました。
この学会は、私が取得している「不妊カウンセラー」の資格発行元でもあり、定期的に参加している大切な学びの場でもあります。
医療や不妊治療に関わる最新の知見に触れることはもちろんですが、今回は元同僚や、現在不妊治療クリニックで働いている友人・知人たちと再会する機会にも恵まれ、非常に実りある時間となりました。
このような学会に参加する動機というのは、「最新の知識を得たい」という専門職としての当然の欲求だけではありません。現場で奮闘している仲間たちとの再会は、自分自身の立ち位置を見つめ直し、これからの活動に新たな視点を与えてくれる貴重な機会でもあるのです。
プレコンセプションケアという視点
今回の学術集会では、特に「プレコンセプションケア」に関する内容が印象的でした。
プレコンセプションケア(Preconception Care)とは、「妊娠を考える前から、自分たちの生活や健康と向き合うこと」です。「コンセプション(Conception)」とは、受胎──つまり赤ちゃんを授かるという意味。これに「プレ(Pre)」が付くことで、「妊娠する前に準備すること」という概念になります。
たとえば、妊娠を望む前から適切な栄養をとり、身体の不調を整え、必要であれば疾患の治療を済ませておく。さらには、パートナーとの関係性やライフプランを見直すことも含まれます。
これまでの不妊治療は、「妊娠を望んでから」のアプローチが中心でしたが、近年は「その前段階」にフォーカスを当てる重要性が高まっています。
カップルが妊娠に向けた準備を日常的に行うことで、治療そのものの負担を軽減できる可能性もありますし、なにより心身の状態をベストな形に整えておくことは、妊娠の確率やその後の経過にも良い影響を与えるでしょう。
多様性に対応するカウンセリング
また、今回特に興味深かったのが、LGBTカップルに対するカウンセリングの内容でした。
日本でも少しずつ制度の整備が進んでいるとはいえ、LGBTQ+の方々が「親になる」という選択肢を実現するには、まだまだ多くの壁があります。それは医療技術の問題というよりも、制度や社会の理解、そしてカウンセリングの在り方といった「支援体制」の整備が求められているということです。
学会では、LGBTカップルが直面する困難や、それに寄り添うためのカウンセリングの手法について具体的な事例も交えて紹介されていました。
カウンセラーとして、ただ「正解」を与えるのではなく、その方が大切にしている価値観や背景に耳を傾ける姿勢が何よりも重要であると、改めて実感させられました。
技術の進歩はひと段落?
個人的な感想としては、ここ最近の不妊治療技術──特に手術や投薬といった「医療的なアプローチ」は、ある意味で一段落したのではないかと感じました。
もちろん、日々研究は進んでおり、細かな改良や安全性の向上は続いています。しかし、過去10〜20年の間に見られたような「画期的な新技術」が頻繁に登場する時代は、少し落ち着きを見せている印象です。
この感覚を裏づけるかのように、今回のシンポジウムでは、技術的な話題よりも「心」や「価値観」に関するテーマが多く取り上げられていました。
ゲストスピーカーには作家の方が招かれ、科学的な情報というよりは、当事者のリアルな想いや葛藤に焦点をあてた講演が行われました。
こうした流れからも、「治療の精度」だけでなく、「治療を受ける人の人生そのもの」に寄り添うことが、今後ますます大切になってくるのではないかと感じています。
治療が「標準化」された今だからこそ
もう一つ、興味深いと感じたのが「保険適用後の不妊治療の変化」です。
保険診療の対象になったことで、多くの方が治療を受けやすくなった一方で、治療内容には一定の制限がかかるようにもなりました。言い換えれば、「画一化・平均化」された側面もあるということです。
これは、以前のような「その人に合わせた個別性の高い治療」がやりにくくなってきていることを意味します。
その中で、私たち補完医療の担い手──鍼灸や栄養療法、ピラティスや整体などが果たす役割が、以前にも増して重要になってきていると感じています。
鍼灸・体質改善が果たす役割
不妊治療において、妊娠の「確率」を高めるためには、体質改善が大きな鍵となります。これは、ただ一時的に身体の状態を整えるということではありません。
生活習慣やストレスマネジメント、ホルモンバランスの調整、自律神経へのアプローチなど、包括的に身体を整えることが求められます。
そういった点で、鍼灸をはじめとする東洋医学的なアプローチは、今後ますますその必要性が高まっていくでしょう。
技術の進歩が落ち着いた今、もう一度「人の身体」そのものにフォーカスを当てるべき時期が来ているのではないか──そんなことを学会に参加して感じました。
最後に
今回の学会参加を通じて、私は「不妊治療のこれから」について考える貴重な時間を得ることができました。
プレコンセプションケアやLGBTQ+支援、そして保険制度と治療の関係。医療の最前線を支える技術と、それを受ける人々の思い。その両方に目を向けながら、自分自身の立ち位置を確認することができたように思います。
そして、今後も補完療法の一翼を担う者として、ただ身体を整えるだけでなく、「心と身体をつなぐ架け橋」として、クライアント一人ひとりに寄り添っていきたいと、あらためて感じました。