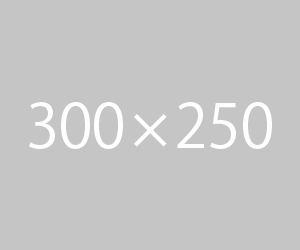私が不妊鍼灸専門の鍼灸院で働き始めたころ、不妊治療はまだ保険適用外で、
「治療費だけで車が一台買える」といわれるほど高額なものでした。
助成金制度はあったものの、その額は決して十分とはいえず、多くのご夫婦が経済的な理由で治療を断念せざるを得ない現実がありました。
それから年月が経ち、私自身が開業する頃には、ついに不妊治療が保険適用の対象に。
初期は制度の混乱もありましたが、少しずつ現場も制度に慣れ、仕組みが整ってきたように感じます。
今回は、そんな保険適用前と適用後の不妊治療の変化について、鍼灸師としての現場の視点と、個人的な体験を交えて綴ってみたいと思います。
保険適用前:高すぎる治療費と限られた選択肢
保険適用前、不妊治療はすべて自費診療でした。
タイミング法から人工授精(AIH)、体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)に至るまで、その費用は1回あたり30〜100万円、治療が長期化すれば数百万円に達することも珍しくありませんでした。
そのため、「お金が尽きてしまい、治療を諦める」という声もよく耳にしました。
ある調査では、約54%の若年層カップルが経済的理由から治療継続を断念していたというデータもあります。
保険適用後:経済的負担の軽減と若年層への広がり
2022年4月、不妊治療の保険適用が開始され、人工授精・体外受精・顕微授精などが一定の条件下で3割負担となりました。
これにより、1回あたりの自己負担額は8〜20万円程度に抑えられるようになり、多くのご夫婦にとって治療へのハードルが下がったのは間違いありません。
実際、あるアンケートでは「治療費が減った」と答えた人が43%にのぼり、
「これまで受けられなかった治療を受けられるようになった」といった喜びの声も多く見られました。
さらに、治療を受ける年齢層にも変化が出ています。
たとえば、福岡県北九州市のある不妊治療専門医院では、採卵を行う患者さんの平均年齢が39.13歳から37.95歳へと2歳近く若返ったという報告もあり、早期に治療を始める若年層が増えてきているようです。
保険適用後に見えてきた課題
保険適用には大きなメリットがある一方で、現場ではいくつかの課題も感じています。
1. 標準化と柔軟性のジレンマ
保険診療では治療が標準化されるため、どの医療機関でも一定の品質が担保される反面、
患者ごとの状況に応じた柔軟な治療が難しくなるケースもあります。
例えば、「複数の受精卵を凍結保存する(貯卵)」などの治療は保険適用外で、全額自費。
私が担当したあるケースでは、妊娠率を高めるための特別な処置が保険適用外であったため、保険診療を断念せざるを得ませんでした。
また、混合診療(保険診療と自費診療の併用)が禁止されているため、保険適用の治療と自費の治療を同日に行うことができず、別日に通院することになったり、周期によって保険適応だったりそうでなかったりするケースがあったりします。
2. 助成金制度の廃止と新たな負担
保険適用が始まったことで、従来の不妊治療助成金制度は廃止されました。
そのため、保険適用外の治療を選択する場合には、かえって以前よりも費用がかさむこともあります。
実際、アンケートでは「保険適用後、治療費が増えた」と答えた人も約30%にのぼりました。
我が家でも、第一子のときには助成金を少額ながら受けられましたが、
第二子のときには制度が変わっていて、治療前の検査一式が自費となり、想定以上の費用がかかりました。
これからの不妊治療に求められるもの
不妊治療の保険適用は、多くのカップルにとって大きな前進でした。
しかし同時に、治療の柔軟性や選択肢の幅、そして費用面での新たな課題も生まれています。
個人的には、混合診療の解禁が最も現実的な解決策だと感じていますが、
これは保険診療全体に関わる制度であり、すぐに変えることは難しいかもしれません。
それでも、「一人でも多くの方に、納得のいく治療を受けてもらえる環境づくり」を目指して、
制度が少しずつでも柔軟に変化していくことを願っています。