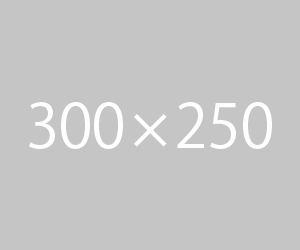少子化が進む日本で、今あらためて考えるべきこと
少子化が叫ばれて久しい昨今、国の将来を憂う者として、出生数の減少は看過できない問題です。
数年前、出生数が100万人を下回ったことが大きく報じられましたが、その後も減少は止まらず、あっという間に80万人を切りました。
そして2024年、日本の出生数は72万988人となり、前年から約3万7,643人(約5%)の減少。
これは9年連続で過去最少を更新する記録であり、統計開始の1899年以降、最も低い数字です。
しかもこの数字には外国人も含まれており、日本人だけの出生数は約68万5,000人と推定されています。
この深刻な状況は、不妊治療を含む生殖支援の重要性を改めて浮き彫りにしています。
とはいえ、婚外子が少ない日本においては、生殖支援以上に「婚姻支援」が優先されるべきかもしれません。
出生数と婚姻数の減少の相関性
厚生労働省の人口動態統計によると、2024年の出生数は前年より約3万7,000人(5.0%)の減少。
一方、死亡数は161万8,684人と出生数を大きく上回り、自然減は18年連続となっています。
婚姻数についても、2024年は49万9,999組と、戦後2番目の少なさ。
参考までに、婚姻数の推移は以下のとおりです:
-
2000年:約80万組
-
2010年:約70万組
-
2019年:約60万組
-
2023年:47万4,717組(過去最少)
-
2024年:やや回復傾向
日本では婚外子が非常に少ないため、婚姻数の減少がそのまま出生数の減少につながっている構図が明らかです。
少子化の背景にある社会構造と意識の変化
直近の婚姻数の減少には、新型コロナの影響も大きかったと思われますが、それ以前からの経済的要因も無視できません。
さらに、
-
「おひとり様」志向の増加
-
非婚化・晩婚化の一般化
-
ライフスタイルの多様化
-
都市への人口集中
-
出会いの場の減少(職場・学校など)
-
お見合い文化の衰退、恋愛至上主義の浸透
といった複合的な要因が絡み合い、結婚・出産に対するハードルが上がっていると感じます。
妊娠・出産への理解不足という問題
仮に結婚できたとしても、晩婚化による妊娠のしづらさや、生殖に関する知識不足がさらなる壁となっています。
実際、私がこれまで接してきた患者さんの中にも、妊娠や生殖について正しい知識を持たない方が多くいらっしゃいました。
特に男性の中には、「性交渉さえしていれば妊娠するだろう」といった、10代のころの感覚のままの方も見受けられます。
一方で、若い頃は避妊を徹底するよう教育されてきたのに、結婚した途端「さあ、妊娠しよう!」という切り替えを求められる…。
これはまるで、学生時代には「従順さ」を求められていたのに、就職活動で突然「個性をアピールしろ」と言われるような混乱を覚えるかもしれません。
未来に向けて必要なこと
少子化に真正面から向き合うためには、目先の政策だけでなく、若い頃からの性・生殖に関する教育の充実が不可欠です。
「結婚したい」「子どもを持ちたい」と思ったときに初めて考えるのではなく、もっと早い段階から生殖に関する知識を身につけ、自分の人生設計に活かしていける環境づくりが必要です。